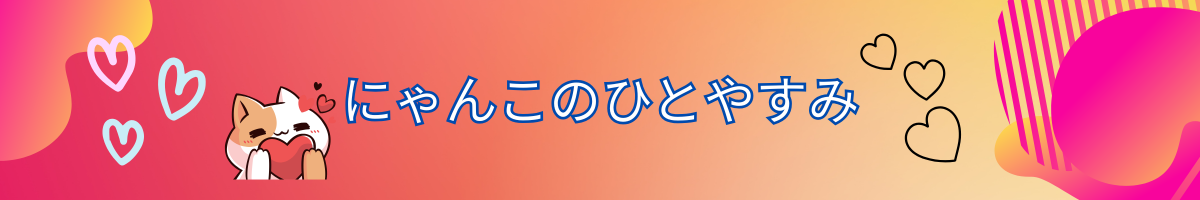夜、台所の灯の下でキャットフードの袋を見つめていた。
「無添加・国産・グレインフリー」と並んだ文字。
言葉の響きだけで“良いもの”に思えてしまうのは、きっと私だけじゃない。
でも封を開けた瞬間、胸の奥で小さな違和感が動いた。
香りが、いつものごはんと少し違う。
うちの子が鼻をひくつかせ、一口めをためらった。
その夜、私は「無添加」という言葉を初めて真っすぐに見た。
十数年、何匹もの猫と暮らしてきて気づいたのは、
“やさしそうな言葉ほど、確認したほうがいい”ということ。
「愛猫飼育スペシャリスト」として学んだ知識と、
暮らしの中で積み重ねた失敗の数々。
その両方が、今の私にこう問いかけてくる。
――無添加って、どこまで信じていいんだろう?
ラベルに並ぶ「国産」「安い」「グレインフリー」「子猫用」。
一見わかりやすいその言葉を、今日は“暮らしの目線”で読み直していきたい。
猫と共に生きる日々の中で、本当に役立つ選び方を見つけるために。
この記事を読むとわかること
- 「無添加」や「国産」などの表示の正しい意味と読み解き方
- グレインフリーや子猫用フードを選ぶ際のポイントと考え方
- 猫の体質や暮らし方に合わせた“無添加”キャットフードの選び方のコツ
猫がもつ“食の本質”を見つめて、素材から考える。
その姿勢を30年以上かけて形にしたのが、アカナ・オリジン。
なぜ「無添加」で選ぶのか?――表示のウラにある法令と実態
キャットフードの棚に並ぶ「無添加」の文字。
この言葉を見て、ふっと手が止まること、ありませんか?
私自身、猫と暮らしてきた中で、“無添加”という言葉に何度も立ち止まってきました。
「なんだか体によさそう」「余計なものが入っていなそう」──そう思うのが自然だと思うんです。
でも、実際に調べていくと、“無添加=すべて何も入っていない”ではないことが見えてきます。
農林水産省のペットフード安全法Q&Aには、
「無添加」「不使用」と表記する場合には、具体的に“何を使っていないか”を明記しなければならないと書かれています。
たとえば「保存料無添加」と書いてあっても、
他の酸化防止剤や風味づけ成分が入っているケースもあります。
私がこの事実を知ったとき、ちょっとショックでした。
“無添加”という言葉を信じきっていたわけではないけれど、
思っていたよりもずっとルールが複雑で、「なるほど、そういう仕組みなんだ」と膝を打ったんです。
そしてさらに掘り下げていくと、ペットフード公正取引協議会の表示基準にたどり着きました。
ここには、「添加物が全工程で使われていない場合のみ“無添加”と表示できる」と明確に書かれています。
つまり、原材料の調達から製造・包装まで、どこかで添加物が関わっていたら“完全な無添加”とは言えない、という考え方です。
このルールを知ってから、私はラベルを見る目が変わりました。
表の「無添加」の文字だけで判断せず、裏面の成分欄をじっくり見るようになったんです。
「香料」「調味料」「酸化防止剤」――小さな文字ほど、猫の暮らしに影響する情報が詰まっています。
でもね、「無添加じゃない=悪い」ではありません。
大切なのは、“何をどう使って、どうバランスを取っているか”を知ること。
無添加の中にも、保存性や風味を工夫している製品もあります。
そこを見極めるには、ラベルを“読む”よりも、“理解する”ことが大事なんです。
無添加表示の落とし穴:「何を無添加にしたか」で全く違う
同じ「無添加」でも、「保存料無添加」「着色料不使用」「香料不使用」など種類はいろいろ。
ある製品では香料を控えて素材の香りを活かしているけれど、
別の製品では酸化防止剤を使わない代わりに包装技術で鮮度を保っている。
つまり“どの添加物を抜いたのか”で、意味がまったく違うんです。
この違いを知ると、ラベルの見方が一段深くなります。
「保存料無添加」だけで選ぶのではなく、
その裏にある“どうやって品質を保っているのか”という工夫まで見えてくる。
それこそが、猫と暮らす人に必要な知識だと感じます。
「完全無添加」はほぼ存在しない?
“完全無添加”という表現を聞くと、すごく理想的に聞こえますよね。
でも実際には、ペットフードにおいてそれを実現するのはほぼ不可能に近い。
原料自体に加工助剤が使われていたり、運搬時の酸化を防ぐための処理がされていることもあるからです。
大事なのは「足し算」よりも「引き算の意図」。
つまり、なぜその添加物を使わないのか、どんな意図で引いているのかを知ること。
この視点があるだけで、広告やレビューに流されず、自分で納得できる選び方ができます。
“無添加”を信じる前に、まず「理解する」
私は、「無添加だから良い」ではなく、
“この無添加がどんな考えで作られているのか”を知ることこそが大事だと思っています。
その一歩を踏み出すだけで、選ぶ時間が「迷い」から「納得」に変わるんです。
ペットフードは毎日のこと。
だからこそ、「表示を読む力」は暮らしの質を左右する。
猫にとって一番うれしい食卓をつくるための、最初の一歩が“ラベルの読み方”なんです。
「国産」「安い」「市販」――表示と価格に惑わされない選び方
「国産」って聞くと、なんだかほっとする響きがありますよね。
でも、にゃんこのごはんの世界では、この“国産”という言葉が思った以上に広い意味を持っているんです。
たとえば、パッケージに堂々と「国産」と書いてあっても、原料の肉や魚は海外から来ていることもあります。
最終的に日本で加工すれば「国産」と表示できる──これはルール上、間違いではありません。
でも、「国産=すべて国内原料」と思い込んでいると、ここで少しズレが生まれます。
私は以前、表示の裏側を調べてみたときに、製造者と販売者が違う商品が多いことに気づきました。
この“違う会社”という部分に、猫のごはんの設計思想が現れることもある。
作っている場所・仕上げている場所・売っている場所――この3つを頭の片隅に置くだけで、見える景色ががらっと変わるんです。
「国産」と書かれているから選ぶのではなく、「どこで、どんな工程を経て“国産”と名乗っているのか」を知る。
それが“選び方の第一歩”だと感じています。
“安い”の意味を掘り下げる――値段の裏には理由がある
「無添加で国産なのに、この値段?」と一瞬テンションが上がること、ありますよね。
でも、値段って、ただの数字じゃなくて“作り手の哲学”が出る場所なんです。
安いものには、安くできる理由がある。
それは決して悪いことじゃないけれど、「どこを削って、どこを残したのか」を見ていくと、製品の個性が浮かび上がります。
たとえば、タンパク源をミール中心にしてコストを抑えていたり、包装を簡略化して価格を下げていたり。
そこに“工夫”があるのか、“妥協”なのかを見分けるのが、選ぶ側の腕の見せどころ。
私の中では、“安い=怪しい”ではなく、“安い=設計のヒントがある”という考え方に変わりました。
なぜこの価格なのか、その背景を想像してみると、ラベルの文字が一気に立体的に見えてくるんです。
「市販」で出会う“現実”――手に取りやすいものほど奥が深い
スーパーやドラッグストアのペットフード棚を歩いていると、つい目が泳ぎますよね。
カラフルなパッケージ、期間限定の味、そして「無添加」「国産」のラベル。
手に取りやすいということは、それだけ多くの人が求めているということ。
市販の商品が“悪い”なんてことはまったくありません。むしろ、継続して買えるという強みがあります。
ただ、よく見ると、同じシリーズでも販売場所や時期によって、原材料の並びが少し変わることも。
私はこの小さな変化に気づくたび、「メーカーもちゃんと試行錯誤してるんだな」と感じます。
パッケージの裏側には、香料・酸化防止剤・着色料などの表記が小さく並びます。
ここを丁寧に見ていくと、商品ごとに“どこを削り、どこを工夫しているか”が見えてくる。
つまり、「市販=一般的」ではなく、“選び方次第で、個性を見つけられる場所”なんです。
「表示を読む」から「表示で見抜く」へ
私は、表示を読むことは単なるチェック作業じゃないと思っています。
ラベルには、作り手の考え方が詰まっているから。
「国産」と「無添加」と「安い」の3つが並んでいたら、まずは「どの要素を一番大切にしたいか」を決めてみてください。
猫の年齢、体質、生活リズム――その条件によって、ベストバランスは違ってきます。
“国産だから良い”“高いから良い”“市販だから気軽”──そんな単純な線引きよりも、
「この設計なら、うちの子の暮らしに合いそうだな」という感覚を育てるほうがずっと現実的です。
ラベルの言葉をただ信じるんじゃなく、“読み解く”。
それが、猫と暮らす人が持てるいちばんの強みだと思っています。
猫がもつ“食の本質”を見つめて、素材から考える。
その姿勢を30年以上かけて形にしたのが、アカナ・オリジン。
グレインフリーって要るの?――穀物不使用のメリットとデメリット
「グレインフリー」って、ペットショップでもネットでもやたら見かけるようになりましたよね。
ラベルの響きがどこかカッコよくて、“なんだか良さそう”と思ってしまう。
でも、調べれば調べるほど、「これは全員に必要なの?」という疑問に行き着くんです。
私も最初は、猫が本来“肉食動物”だから穀物を抜くのが自然なんじゃないかと感じていました。
けれど、獣医栄養学の考え方を読み込むうちに、グレインフリーは“誰にでも良い魔法の言葉”ではないと知りました。
むしろ、猫の体質や暮らし方によって「向く・向かない」がハッキリ分かれるテーマなんです。
“穀物ゼロ”が目的じゃない――そもそもグレインフリーの設計意図
グレインフリーとは、文字通り「穀物(グレイン)を使っていない」設計のこと。
米・小麦・とうもろこしなどを抜く代わりに、じゃがいもやエンドウ豆などで炭水化物を補う仕組みです。
だから、「穀物ゼロ=炭水化物ゼロ」ではありません。ここを誤解している人、実はすごく多いです。
メーカーのヒルズ公式ガイドでも、「穀物を抜くことで特定の猫にメリットがある一方、必ずしもすべての猫に必要ではない」と明記されています。
つまり、グレインフリーの本質は“流行”ではなく、“必要性の見極め”なんです。
アレルギーの可能性がある猫、消化がゆるくなりやすい猫にはメリットが出やすい設計ですが、そうでない子の場合、穀物を抜くことで別の栄養バランスが崩れることもあります。
要は「抜くこと」より「どう補うか」――これが肝なんです。
体質によって合う・合わないが出る理由
猫の体は本来、たんぱく質中心で動く仕組みをしています。
でも、たんぱく質ばかりでは消化の流れが偏ってしまうことも。だから少量の炭水化物を加えてバランスを取るフードが多いんです。
グレインフリーが合うと言われるケースは、主に以下のような子たち。
・小麦やトウモロコシなどの原料に反応しやすい猫
・便がゆるくなりやすい、もしくは皮膚が荒れやすい猫
一方で、健康な成猫や高齢猫には、穀物由来のビタミン・ミネラルがかえって役立つこともあります。
だから、ラベルの「グレインフリー」に飛びつく前に、「うちの子が穀物を食べて困っているか?」を一度立ち止まって考えてみること。
この“見極めのワンステップ”が、選ぶ力を確実に育ててくれます。
グレインフリー=贅沢品?その誤解をほどきたい
グレインフリーって、値段の印象で「高級路線」と感じる人も多いと思います。
でも実際は、使用するたんぱく源や炭水化物の種類が異なるだけで、価格が上がるのはその分の原料コストが関係しているんです。
ここで注目してほしいのは、「値段=価値」ではなく、「設計=意図」だということ。
どんな材料を使い、どうやって猫の栄養バランスを作っているのかを知ると、ラベルの見方が変わります。
グレインフリーのよさは、“流行りだから選ぶ”ではなく、“必要な子にしっかり届くよう作られている”という点。
この考え方を知るだけで、情報の波に流されず、自分の軸で選べるようになります。
キーワードは「猫を観察する」
ラベルよりも先に見るべきなのは、猫そのものの変化です。
毛づや、食後の様子、便の状態――その小さなサインが、フードの相性を教えてくれます。
グレインフリーが合う子は、「食べ方」や「体の軽さ」がわかりやすく変わることもある。
でも、合わない場合は少しずつ違和感が出る。食欲が落ちたり、便が硬くなったり。
つまり、「グレインフリーを選ぶ」ことよりも、「猫の反応を見ながら調整する」ことが本当の意味でのケアなんです。
表示はきっかけ、正解は猫の姿の中にあります。
グレインフリーの正解は“その子の暮らし”にある
猫の世界にも“流行”はあります。
けれど、私たちが選ぶべきなのは「流行」ではなく、「うちの子の暮らしに合うリズム」。
グレインフリーも、国産も、無添加も。
それぞれに理由があって生まれた設計だからこそ、飼い主が「なぜ」を理解してあげることが大切です。
ラベルの言葉を読むのは、メーカーを信じることではなく、猫と暮らす時間をより豊かにするための学び。
私は、そんな目線で「グレインフリー」という言葉を見つめ直しています。
子猫にはどう選ぶ?――「無添加子猫用」の本質
子猫のごはん選びほど、飼い主の性格が出るテーマはないかもしれません。
小さな体に、あの小さな歯。毎日少しずつ大きくなる姿を見るたびに、
「これで足りているのかな」「もう少し良いものを」と考えるのが、猫と暮らす人の性。
でも、ラベルに“無添加”と書いてあると、どこかでホッとしたような気持ちになる。
私もかつて、そう感じたことがあります。だけど――
子猫期のフード選びは、“無添加”という言葉の響きよりも、「栄養設計の中身」を見ていくほうがずっと大事なんです。
子猫の体は「吸収の天才」――だからこそ栄養密度で選ぶ
子猫の体は、たった数か月で筋肉も骨格も内臓もぐんぐん育ちます。
つまり、大人の猫よりも“必要な栄養の濃さ”が違う。
この時期に注目すべきなのは、たんぱく質・脂質・カルシウム・DHAといった「成長を支える軸の栄養素」。
例えばDHAは、脳や神経の発達に関わる大切な成分。脂質はエネルギー源として欠かせません。
「無添加子猫用」と書かれていても、
これらの栄養素がしっかり確保されているかは、ラベルを見ないとわからない。
ここで大切なのは、「無添加=削る」ではなく「必要なものを残して設計する」という考え方。
“添加物を控える”ことと、“栄養を減らさない”ことは別の話なんです。
「成猫用」で代用しない理由――ほんの少しの差が大きな違いに
成猫用と子猫用、見た目は似ていても中身の設計はまったく違います。
特に脂質とたんぱく質の配合。子猫期に必要なのは、成猫よりも高めのエネルギー密度です。
体を作る材料が足りないと、筋肉や骨の発達にブレーキがかかってしまう。
ある栄養士さんの話では、「子猫用のフードは“成長のための濃縮設計”」と表現していました。
この一言にとても納得しました。
だから、たとえ“無添加”を重視しても、子猫期だけは「子猫専用設計」で探してほしい。
これは数年後の健康を見据えるうえで、すごく重要なポイントです。
“無添加子猫用”の見方――見るべきは「バランス」と「意図」
最近は、「無添加子猫用」と書かれた商品も増えました。
ただし、ラベルの印象に惑わされないでほしい。大事なのは、その裏側の考え方。
たとえば、人工香料や着色料を使わず、素材の香りで食いつきを工夫しているもの。
あるいは酸化防止にビタミンEを使って、化学的な保存料を避けているもの。
どちらも“無添加”ですが、アプローチがまったく違います。
つまり、「何を無添加にして」「何で補っているのか」。
そこを知ることで初めて、“無添加”という言葉が生きてくる。
単に「やさしそう」ではなく、“どう設計されているか”で判断する目を持つことが、
子猫の成長を支える大切な選び方になります。
「無添加=やさしい」ではなく、「無添加=工夫されている」
私は、この考え方を知ってから、ラベルの見え方がまるで変わりました。
“やさしそう”という感情だけではなく、「この設計にはどんな意図があるんだろう?」と興味が湧くようになったんです。
無添加とひとことで言っても、
それはメーカーが「素材の力で勝負する」と決めたということ。
つまり“削る”というより、“見せ方を工夫している”のです。
そう思うと、フード選びがちょっと楽しくなりませんか?
「うちの子に合うのはどのタイプかな」と想像しながらラベルを読む時間が、
ただの選択から“猫と暮らす知恵の時間”に変わっていく。
子猫の時期こそ「無添加=設計の考え方」で選ぶ
子猫の食事は、未来の体を作る“設計図”そのもの。
だからこそ、ラベルの言葉に頼るよりも、その裏にある設計思想を読み取ることが大切です。
「無添加だから良い」ではなく、「何をどう残して、どう削ったか」。
この視点を持つだけで、子猫期のフード選びはぐんと楽しく、意味のあるものになります。
にゃんこと暮らす時間はあっという間。
小さなごはん皿の上にも、“これからの健康を支える工夫”が詰まっています。
その見えない部分を想像しながら選ぶこと――それが私の考える「無添加子猫用」の本質です。
おすすめ?それともあえて選ばない?――私の“無添加”比較メモ
ここまで読んでくださった方は、きっとこう思っているはず。
「で、結局どれがいいの?」って。
わかります。私も昔はそうでした。
“おすすめ”という言葉にすぐ目がいって、ついランキングや口コミを片っ端から見ていた時期がありました。
でも、長く猫と暮らしてきて感じたのは──
「おすすめ」よりも「相性」こそが、フード選びの本質なんです。
にゃんこの暮らしは十匹十色。
だから、“一番いい”は存在しません。
ある子にとって理想的なごはんが、別の子には全然合わないことも普通にある。
それを何度も目の前で見てきて、「無添加」という言葉の意味を自分なりに捉え直すようになりました。
「暮らしとの相性」で選ぶ――パウチか、大袋か、それとも小粒?
無添加のフードを選ぶとき、まず考えたいのは“暮らしの形”。
たとえば、一匹で暮らす猫と、多頭飼いの家庭ではフードの減り方がまるで違います。
開封から食べきるまでのスピードが違えば、保存状態も変わってくる。
パウチタイプは、香りの立ち方や扱いやすさが魅力。
一方で、大袋タイプはコスパが良いけれど、開封後の扱い方次第で品質に差が出やすい。
ここに「保存料少なめ」という要素が絡んでくると、管理の仕方も含めて“暮らしの工夫”が求められるんです。
つまり、フード選びは「無添加」だけを軸にするのではなく、
暮らし方との相性を重ねて見ていくもの。
そこに“その家らしい選択”が生まれると思っています。
“安い無添加”の中にも光る選択がある
「無添加」と聞くと、どうしても高級フードを想像しがちですよね。
でも、価格が低めのものにも、きちんと工夫された設計があります。
たとえば、原材料の種類を絞ってコストを抑えているもの。
または、パッケージデザインや広告費を減らして、価格を落としているブランドもあります。
こういう部分って、実際に調べてみると“企業の誠実さ”みたいなものが透けて見えてくるんです。
私がよく言うのは、「安い=悪い」ではなくて、
「安さの中に“考え”があるか」を見ること。
ラベルの裏側を読むのは、まるで作り手と会話しているような感覚です。
そうやって選んだフードは、値段以上の納得をくれることが多いんですよ。
市販ブランドの“無添加”は、工夫のかたまり
「コンボ無添加」などの市販ブランドにも、最近は“挑戦”が感じられます。
どこまで添加物を減らせるか、どんな素材で香りを引き出すか──そうした研究の積み重ねがある。
それを知ると、ラベルの「無添加」という言葉が、単なる装飾じゃないことに気づきます。
ただ、すべての猫に同じように合うわけではありません。
香りや粒の硬さ、口当たりの違いで、食べ方に差が出ることもある。
そんな時は「うちの子のペースに合わせて調整する」くらいの気持ちで、少しずつ試していけばいいんです。
“合わない=失敗”ではなく、“見つけていく過程”。
それが、無添加フードと上手に付き合う一番の近道です。
“おすすめ”を求めないという贅沢
私は、「これが一番!」と断言する記事よりも、
「うちの子にはこう選んでみた」というリアルな選択の話の方が好きです。
無添加フードの世界は、あまりにも多様。
だからこそ、「選ばない理由を知っておく」ことも大事な選択肢だと思います。
ラベルの言葉をうのみにせず、自分の目と感覚で見極める。
私はいつも、こう考えています。
“おすすめ”って、他人が決めた“最適”でしょ?
でも猫と暮らす私たちは、“うちの子の最適”を探す旅の途中にいる。
その旅こそが、にゃんことの時間をもっと豊かにしてくれるんです。
選ぶ軸は「うちの子の暮らしを心地よくするか」
「無添加」「国産」「グレインフリー」「安い」──どれも魅力的な言葉だけど、
最終的に選ぶのは私たちであり、猫たちの暮らし。
大切なのは、“食べる時間を心地よくしてあげられるか”という一点。
私はいつも、フードを選ぶたびにこの言葉を思い出します。
ラベルよりも、猫の表情。
価格よりも、食べるリズム。
そして、流行よりも、“うちの子に合う”という実感。
その視点さえあれば、どんな選び方をしても間違いじゃない。
だって、「無添加」を選ぶ目的は、“猫と心地よく暮らすこと”そのものだから。
まとめ
“無添加”はゴールではなく、選び方のスタートラインでした。この記事では、ラベルの「無添加」「不使用」は何を指しているのか、表示の読み方(国産=最終加工の概念、価格の裏にある設計、店頭やECでの見え方)、グレインフリーが“誰にでも正解”ではない理由、そして子猫期こそ栄養設計を軸に見る重要性を、暮らし目線で整理しました。
私が強く思うのは、言葉よりも“うちの子のサイン”を観察すること。原材料の並び、成分値、粒の大きさや香り、保管しやすさ──小さな要素の積み重ねが、その家の食卓にちょうど良い一皿をつくります。
「国産」「安い」「グレインフリー」「子猫用」「市販」…どれも選択のためのヒント。正解はひとつじゃないから、他人の“推し”より、自分の基準を育てましょう。
結局のところ、選ぶって難題じゃない。“猫の暮らしに役立つかどうか”を軸に、ラベルの意味をほどき、目の前の変化に合わせて微調整する──その繰り返しが、にゃんことあなたの毎日を軽やかにしてくれます。
参考情報・出典
- 農林水産省|ペットフード安全法 Q&A(表示の基準)
- ペットフード公正取引協議会|表示に関する公正競争規約
- ヒルズ公式|グレインフリーキャットフードの考え方
- アンチエイジングネットワーク|国産表記の注意点
※本記事は各公式機関・メーカーの公開情報を基に構成しています。
医学的・栄養学的な判断を目的とするものではなく、猫との暮らしを見直すための参考情報としてお読みください。
猫がもつ“食の本質”を見つめて、素材から考える。
その姿勢を30年以上かけて形にしたのが、アカナ・オリジン。